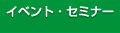南米ニュース 新着30件
2014年5月8日 18:00
深刻化する食糧危機
2008年以降、ベネズエラでは食糧危機が深刻な問題となり、年々、深刻度を増している。昨年には、食糧危機は臨界レベルの国家問題となった。厳しい統制や米ドル不足によりミルク、小麦、サラダ油、トイレットペーパーなど輸入が困難となり、国内では特定品目(ミルク、サラダ油、砂糖、黒豆、小麦粉)をはじめ、慢性的な商品不足状態であるという。
財務副大臣ラファエル・ラミレス(Rafael Ramirez)はニコラス・マデュロ(Nicolas Maduro)政権の責任を否定しているが、食糧危機に対する政府政策や国家法案が裏目に出て、事態の深刻化に拍車をかけたと考えられている。
(画像はイメージです)
食糧危機の要因となった政府政策と国家法案
食糧危機を深刻化させた要因として、政府発行の「Eカード」が指摘されている。「Eカード」とはIDカードであり、不正価格での転売を目的とした買い溜めを禁止する目的で2014年4月1日より運営を開始した。3万人以上の個人情報と認証用指紋が登録され、このIDシステムにより政府は国営店舗での各家庭の購入金額・内容を把握でき、国民は毎日同じ商品を購入することを禁じられるという。
また、先週、ニコラス・マデュロ(Nicolas Maduro)大統領は、食糧危機は食糧輸入に関する書類業務の簡略化、地方の民間部門に対するパラレル・ファンド方式の導入といった国家法案に起因するとの見解を発表した。
政府による価格統制の必要性
ウゴ・チャベス(Hugo Chávez)前大統領は、貧困層の生活救済のために価格統制を実施していた。現在、ベネズエラの街頭商人らは、適正価格や価格法則に基づく価格をはるかに上回った価格にて食糧雑貨を販売し、利益を得ている。
例えば、サラダ油は適正価格10.69BSに対して、街頭では10倍以上の価格で販売されていた。(2014年4月時点、サラダ油欠品率100%)
現状改善のためには、当分の間、ベネズエラ政府が価格統制を行う必要がある。政府は不正な価格上昇を厳しく取り締まると公言したが、状況は全く改善されていない。
babalublog
http://babalublog.com/
the guardian
http://www.theguardian.com/
-->
記事検索
アクセスランキング トップ10
特集
お問い合わせ